以前からめちゃくちゃ気になっていた本を、ついにAmazonでポチッと押してしまった。
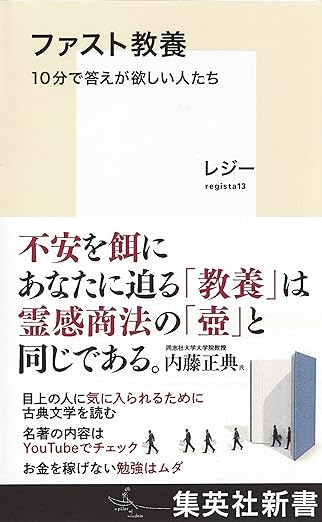
タイトルを見てすぐに「これは買わなければ」と思っていた本だった、届いたときには胸が躍りほくほくしながら読んだ。
この本のタイトルと表紙から、わたしがここ数年ずっと胸の中でくずぶっていた苦々しいもどかしい思いを言語化してくれるのではないかという期待を抱いていたが、予想以上だった。面白すぎた。
まさにこれこそがわたしが追い求めていた本だと思い貪るように読み久しぶりに本がマーカーでいっぱいになった。
「ファスト教養」とは。
このタイトルにある「ファスト教養」とは筆者であるレジーさんの造語であるらしく、
ファストフードのように簡単に摂取でき、「ビジネスの役に立つこと大事」という画一的な判断に支えられた情報。
(「ファスト教養」p10)
というのが大体の定義であるらしい。昨今の世に出ている「教養」といえば、こうしたイメージの方が強いのではないだろうか。
Youtubeにあがっている古典やビジネス書の要約。名作映画をダイジェストに切り抜きしまとめた映画チャンネル。書店に所狭しと並んでいる「教養としての○○」という本(中身はだいたい名作と呼ばれる古い作品の名前と概要の羅列)。
だいたいこうしたコンテンツは本であればベストセラー になっているし動画であれば再生数がものすごく高い。つまりそれほどいまはこの「ファスト教養」が多くの人間に支持されているということだろう。
ビジネス系教養インフルエンサーが作った日本の「教養」。
そしてそうした「ビジネスを中心とした教養」の流れを作り支えているのが以下のインフルエンサーたちである。
ひろゆき、中田敦彦、カズレーザー、DaiGo、前澤友作、堀江貴文。
この名前の列挙からこの本は始まるのだが、この名前の集まりを見て反射的に「うわあ……」と顔を顰める方と、わくわくと胸を高鳴らす方の二手に分かれると思う。
どうやらこの本は、主に前者の人間に向けて作られているようである。もし後者の方がこの記事を読んでいたらここで読むのをやめることをお勧めする。
この面々は、二〇二一年の年末のエンターテイメントサイト「モデルプレス」で発表された「ビジネス・教養系YouTuber影響力トレンドランキング」の上位陣である。 ここまでの文字列に、なんとも言えない居心地の悪さと日本の「教養」への不安を覚える人は少なくないのではないか。(「同上」p8)
まさにこのように反射的に不安を感じる人間はこの日本に多いとは思うが(そう信じている)、しかしこの方々が相当な数の人間から支持を得ているのも事実である。
おそらくいま、こうしたいわゆるインフルエンサーと呼ばれる方々の支持派と嫌悪派において分断が起こっており、それにともない「教養」をめぐっての論争もこの二つの派閥のあいだでたびたび起こっている印象である。
世はまさに「教養混乱時代」と言えるのではないだろうか。
では、「ファスト教養」を排除し「古き良き教養」を取り戻すべきか?
「教養」についての議論はたびたび上がっている。
そのときによく問題となるのが、「ビジネスに役立つツール」として「教養」の名を出すのは如何なものか、というものである。
わたしはこういう「ビジネス中心教養」に対して否定派だが、しかし支持しているひとたちを批判し嫌悪し排除したいわけではない。
ファスト教養が流布している今の状況は批判的に捉えられるべきというのが筆者の基本的な意見である。ただ、だからと言って、ビジネス系インフルエンサーを見下し、「古き良き教養に戻れ」といったメッセージを出したところで何の役にも立たないこともよく理解しているつもりである。(「同上」p12)
この本のすばらしいところは、この著者もどちらかというとこういう「ビジネス系の教養」に対して否定派であるにも関わらず、かといってやみくもにこうしたビジネス系教養インフルエンサーを見下したり馬鹿にしたりせず、ちゃんと理解を示した上で、「こうしたものが支持されている今の時代背景には何があるのか」「それの何が問題なのか」「では、これからどうしていくべきか」ということを冷静かつ具体的に述べているところである。
上にも書いたようにわたしは否定派である。
だが同じく否定派の方たちがビジネス系インフルエンサーを嫌悪し見下し、「昨今の教養の軽さ」を嘆き、「古き良き教養」があった昔のように古典や名作を読むことを闇雲に勧めるのも違和感を覚える。
そういう「古き良き教養」も完璧ではなく、当然欠陥もあった。
そのことについては、いくつかの本の中で指摘されている。
まず、従来の人文的教養には、少数エリートに独占されがちという根本的欠陥がありました。哲学や古典を学ぶことは、誰にでもできることではないからです。(中略)
こういった教養を身につけた知性溢れる人間は当然少数となります。知性は独裁者や軍事政権などにとって目の上のたんこぶですから、少数勢力だとあっという間に沈黙させられてしまいます。(「国家と教養」p176)
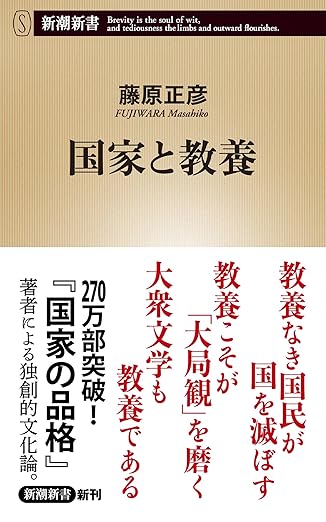
教養主義は不寛容性に対しては革新的、だけど、大衆に対しては差別的。つまり、相続資本的な教養人と比べて自分は贋作ではないのかという負い目が、他者に投影されることで排他的になるんじゃないでしょうか。そして、同質性の高い集団を形成する。
教養主義派はホモソーシャル的な空間をしばしばともなうし、権威主義化する傾向にあります。教養のない人間を否定する。「仲間」や「同志」の選別が苛烈になりがちです。(「教養主義のリハビリテーション」p194)
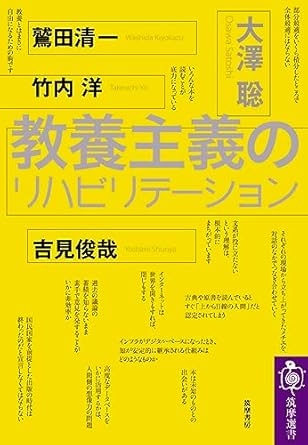
「古き良き教養」は少数エリートしか得られない特権であり、かつ「教養のない人間」への差別や軽蔑を生み出し、さらに「教養のある人間」同士がお互いに仲間であるということを確認し合うためのツールとして「教養」が使われていたという面が多々あったようである。
勿論、「古き良き教養」がすべてそうだった、というつもりは毛頭ない。「古き良き教養」の勧める古典や名作などは素晴らしいものである。
しかしもはや時代が変わり、「教養」というものが一部のエリートだけではなく大衆にも必要となった現代において、「古き良き教養」を美化し称賛しそれがなくなった今の時代をひたすら嘆いていても仕方がないと思う。
「ファスト教養」でもなく「古き良き教養」でもない、「あたらしい時代の教養」とは。
教養を主題とした特集がビジネス雑誌で頻繁に組まれ、新学期ともなれば「教養としての×××」といったテンプレを掲げる書籍が一番に送り出される。そこでは、「明日すぐ役に立つ」ことが対価分きっちりと期待されていて、たいていはその時点での最先端の分野のメニューがならぶ。(中略)
他方、むかしながらの教養論も健在だ。古今東西、時間と空間を自由自在に住還しながら、次から次へと読者の眼を眩まさんばかりにくり出される固有名や引用の数々は、“教養ある話”をいかにも体現していて、対象と語り口がそのまま合致する。であればこそ、読む人間をあらかじめ限定してしまう。(中略)
このふたつの罠を回避した教養論が必要なのではないか。最新の知識をマニュアル化するハウツー路線でもなければ、教養の有無をパフォーマティブに確認しあう共同体路線でもない。そのどちらにも与しない路線の選択。(「教養主義のリハビリテーション」p9)
この本にも書かれているが、これからの時代に大事なのは「ファスト教養」を完全否定するのでもなく「古き良き教養」の復権をひたすら願うのではなく、どちらの要素も兼ね備えたいまの時代にあった「あたらしい教養」を一から作り上げることなのではないか。
どうやらニーチェも似たようなことを考えていたようだし、
ニーチェ は『反時代的考察』(中略)や、遺稿「書かれなかった五冊の書物のための五つの序文」の中で、眼前のドイツの世論を支配する知識人たちを「教養俗物」とこきおろし、辛辣な批判を加えている。彼らは、ぬるま湯のような安楽さにひたりながら、過去の思想遺産を、ただかき集めることに終始する。批判精神に飛んだ歴史記述や、藝術家たちの冒険に富んだ創造を、自分の世界を覆すものとして排除してしまう。(中略)その結果、自分自身をも批判にさらす、力強い知性を養うような、本当の「教養」は見失われてゆく。
ーーレーヴィットは、ニーチェ の「教養」批判の意図が、むしろ「教養」の新たな再建をめざすものであったと指摘する。(「移りゆく教養」p86)
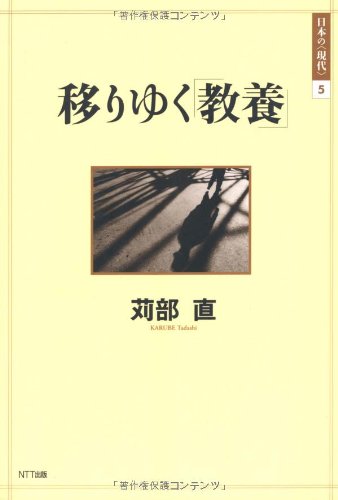
こちらの本のなかでは、日本はこれから「新教養主義」を目指すべきだと述べている。
そして、そうした新教養主義の立場に立つ人間が数多く現れる時代が来た時、日本は文化を大切にする国として真に世界から尊敬される国となることができるであろう。
二十一世紀の日本は「新教養」立国を目指すべきなのである。(「新しい教養を求めて」p18)
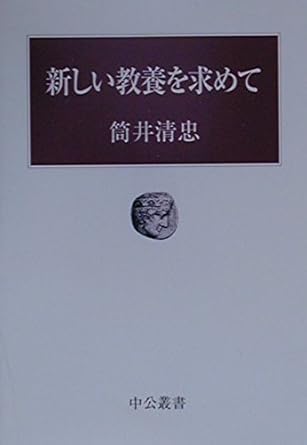
このブログの大きな目的のひとつが、「あたらしい教養」の考察と提案である。
わたしはまさにこのブログにて、日本の「新教養主義」、新時代に向けた「あたらしい教養」についての考察、そして提案をしてきたいと思っている。
「ファスト教養」はいまの時代に適応しすぎているし、「古き良き教養」はいまの時代に適応していない上に問題点も多かった。
勿論、「ファスト教養」にも問題点は多いように思う。だが問題は「ファスト教養」自体にあるのではなく、それが広まり定着しつつある現代社会そのものにあるようだ。
ファスト教養が広まる一番大きな背景は個々人が抱える不安感である。これが払拭されない限り、誰が何と言おうとも今の潮流は続いていく。人々の不安に寄り添い、それを少しでも軽減させるような論こそ、アンチファスト教養、もしくはポストファスト教養の考え方として意味を持つはずである。(「ファスト教養」p184)
「新教養主義」を立ち上げるとして、まずは「ファスト教養」が急速に広まり定着しつつある現代の問題点、そして「古き良き教養」が持っていた欠陥と問題点について洗い出し、その両方を解消しかつ新時代への希望が持てるようなできるだけわかりやすい「あたらしい教養」を提示できるようにしたい。
このブログの最終的な目標はそこにある。
そしてその分析をするにあたり、本書「ファスト教養」は非常に明確かつ、中立で理性的、何より面白く思いやりのある考察が胸の奥底に染み込むようだった。
わたしの視界がまたひとつクリアになったように感じ、自分の向かうべき方向性も見えてきたように思う。
著者であるレジーさんには心から感謝を述べたい。ありがとうございました。